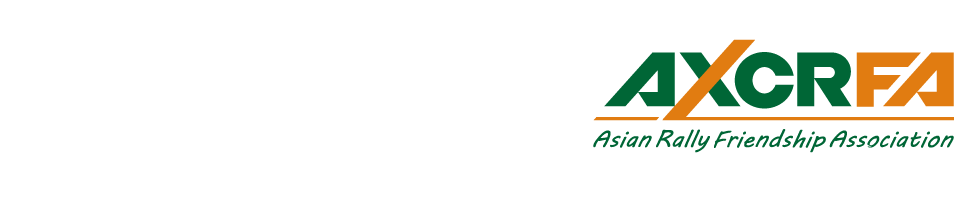LEG4
8月12日(火)プラチンブリ
傷付いたマシンをどこまで直せるか?
休養日のサービスクルー達の戦い
競技4日目、カンボジアとの国境近くで予定されていたSSが安全上の理由によりキャンセルされ、ラリーは休養日となった。
古くからAXCRを知る者なら「ルートを変えればいい」と思うかも知れない。確かに、迅速にコースを変更できた時代もあった。だが今は違う。SSを実施するためには2ヶ月前にセーフティーブックを作り、警官の配置場所など全ての計画を提出する必要がある。今回のような紛争激化のタイミングでは、他に選択肢がなかったのだ。むしろ大会そのものがキャンセルにならなかったことに感謝したい。
この日、四輪の各チームは与えられた1日の大半を修理と整備に費やした。レストデイだからといって観光していたわけではない。まずは移動。ナコーンラーチャシーマーからプラーチーンブリーのホテルへ整備ピットを移し、サービスクルーはそこでマシンを修理し続けることになった。
修理と整備の項目は山ほどあった。なぜならこの3日間の戦いがあまりに厳しかったから。砂埃の中、止まりきれずに前車に追突してしまったマシン。激しい凹凸やジャンプでフロントデフを壊したマシンは数知れず、フロントサスが壊れ、タイヤがあらぬ方向に向いてしまったマシンの数も両手を使って数えねばならぬほど。しかもその理由がドライバーのミスとは言い切れない物も多数。金属疲労から走行中突然にアクスルが折れてしまったマシンもあった。切り株に脚を取られ、ひっくり返ってしまったクルマとて1台や2台ではない。
その他ショックアブソーバーやラテラルロッドが外れてしまったり、ステアリングの異常、ラジエターやトランスファーの故障、スピードメーターやエアコン、ワイパーの故障に、割れた窓ガラスの処理、もげたミラーの交換や曲がったボディパネルの叩き出しなどなど、数え挙げればキリが無い。これら全ての故障を可能な限り修理して後半戦に備えなければならない。
5人の学生達と女性選手4名の真剣勝負!
実はこの大会に、日本から5人の学生がサービスクルーとして参加している。中央自動車大学校(CTS)にて一級自動車整備士を目指して4年間勉強してきた学生達だ。彼らが担当するクルマは PROPAK GEOLANDAR ASIAN RALLY TEAM の新型ジムニー2台。いずれも彼らが4年生となった春から大勢の仲間と一緒に修理や改造、整備をしてきたマシンだ。
この日は予期せぬ休養日。できることならカオヤイ国立公園にでも繰り出して観光でもしたかったことだろう。だが彼らは貪欲に整備を続けた。その合間に壊してしまった備品の買い出しとピットレイアウトの見直し。休む暇などあるわけがない。
そもそも競技初日に1台が転倒したことにより、彼らはいきなり夜昼ない生活に突入した。定時に授業や作業が終わって帰れる学校とは違い、自分達がまる1日真剣に向き合わねば次の朝競技に出ることができない、という状況に追い込まれてしまう。
そんな中、「彼らの動きは日を追うごとに変わって来ていて、自分が何をやらなきゃいけないのか、見えてくるようになってきています」と同校の副校長であり今プロジェクトリーダーの小谷秀則先生は目を細める。そして「自分たちが作った車を実際に過酷な状況下で走らせることで、どの対策が良くてどこがダメだったのか、その因果関係までチェックできます。真剣勝負の場で、学びをさらに深めることができるのは幸せなことですよね」と付け加えていた。
実際に学生達からは、寝不足を恨むような声よりも「めちゃくちゃ楽しい」「よりダメージの大きなマシンからは得られるものが多くて、勉強になる」「こんな経験は滅多に出来ないから、絶対に自分の糧になるはず」と前向きなコメントが多い。
実際のところ真面目な学生が多く、初めは完璧に直せない、直さないことに違和感を感じていた学生が多かったものの、次第に「完璧に直せなくても限られた時間内で翌日走るのに必要な対策を施す」という教科書には載っていないやり方を経験することで、臨機応変に対応する能力が備わり始めているのだという。
そしてもちろん、2台のジムニーを駆る4人の女性選手達も日々、ラリーの厳しさを学びながら前に進んでいる。特に♯137 のショートジムニーを操る 伊藤はづき / 槻島もも 組(日本)は海外遠征はもちろん、クロスカントリーラリーも初めて。想像以上に厳しかった山岳路の洗礼にもめげず、でも時に悔し涙を見せながら、力を合わせて立ち向かっていく姿は、学生達の脳裏に焼き付いているに違いない。
果たして、学生達が夢を乗せ、彼女達がラリー人生をかけて操る2台のマシンは無事パタヤのゴールに辿り着くことができるのか? ワークス勢がガチンコの戦いを繰り広げる大会の裏で、小さなプライベートチームと小さなジムニーが繰り広げる大きな大きな挑戦にもぜひ、注目していただきたい。
(文/河村 大、写真/高橋 学)
Moto
つかの間の休息日。ライダーたちがやることと言えば……?
競技4日目、Leg.4は事前に知らされていた通りキャンセルとなり、参加者に突然の「休息日」が訪れた。たまたまタイ王国でもこの日は「母の日」という祝日だったため、先週の土・日曜日から月曜の「特別休暇」とあいまって4連休となっており、観光地としても有名なカオヤイ国立公園をまたいでの移動では、場所によって多くの観光客でところどころ渋滞が発生していた。
ちなみに、「カオヤイ」とは「Big Mountain」=「大きな山」という意味らしい。確かに移動中、道路上の最高標高地点に差し掛かると視界に広がる光景にその呼び名がしっくりくることに気づく。恐ろしく広大で、深い。
Leg.3の滞在地からLeg.4のホテルへ移動するのみとなったこの日、ライダーたちはチェックアウトの11:00に合わせてゆっくりと朝食を取り、次のホテルまで自走するためのマシンの整備、搬送トラックとサポートカーへ積み込む荷物の仕分けと整理(タイヤや工具、整備に伴う大型荷物などと、着替えなど宿泊に伴う身の回りのもの)など、粛々と準備をこなしていた。
レースではない細かい話、次のビバーク地となる宿泊ホテルのチェックインは15:00で、ルートにもよるがだいたい2時間半で到着するので時間を持て余してしまう。
ライダーたちはまず次のホテルの駐車スペースにパドックを陣取るため、チェックイン前の早い時間に到着し、協力し合って場所取りをする。チームや共有のテントは後発のサポートカーを待つことになるので、何かしらモノを置いてその場所を知らせる。それはまさに日本の夏の風物詩である花火大会で、川沿いの許されたスペースにブルーシートを敷くようなものだ。
チェックインが済むと、ここぞとばかりにランドリー探し。そう、ほとんどのライダーがやることと言えば、泥と汗にまみれた大量の洗濯物をここぞとばかりに処理することだ。そして、なかなか洗い落とせない車体に沁みついた砥の粉のような土の汚れを落とすこと。
ネットで周辺情報を検索、もしくはたまたま見つけた洗車場など、各々が情報を発信し合う。それがいかに安くて綺麗で使いやすくて丁寧な対応の施設を見つけられるのか、まるで競い合っているかのようだ。
お互いにいかに良い情報を共有し合うことを競い合っているとは、まるで順位を上げるために騙し合い、足を引っ張り、蹴落とすための策を講じる競争の側面とはまったくもって相反しているところが非常に興味深い。
そんなこんなで日が暮れて、つかの間の休息日は夕暮れと共に翌日の競技再開に向かって各々スイッチを切り替えていく。
通常であれば、寝る時間を少しでも確保するため整備も妥協せざるを得ないところ、余裕のある時間をもって自車の整備に没頭できるとは「ラッキー」と捉えることが出来る。
しかし、どんなに準備してもけして安心は出来ない。「まさかソレが!?」という経験はライダーであれば何度も経験しているからこそ入念に、「まさか」が無いよう粘っこく整備する。そうしてベッドに横たわり、あとは何も考えずに寝る。何かあったらどうにかするしかない。ここまでやっても起こるときは起こるもの、という割り切りも、精神状態を健全に保つために必要なスキルと言えるだろう。
本来であれば8日間ぶっ通しの過酷な競技だったところ、たまたま「休息日」が挟まれたことに物足りなさを感じる者もいるかもしれない。しかし舞台はタイ王国であり、ビバーク地はすべて星付きのホテルなのだから、そんな環境を「ご褒美」と捉えてバカンス気分を楽しめばいい。そう考えられるのも、アジアンラリーならではと言える。
さてさて、大会5日目はどんな事態が待ち受けているのか、トップライダーたちの走りと順位に動きはあるのか、コマ図の読解に苦しむライダーたちに活路はあるのか、そもそも天候はどうなのか……。
アジアンラリー30周年記念大会は、明日から後半戦が繰り広げられる。
(写真・文/田中善介)