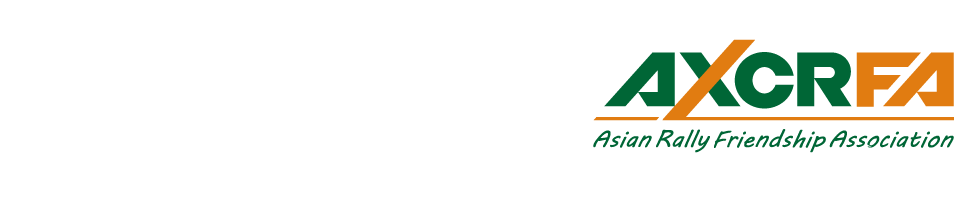LEG1
8月9日(土)プラチンブリ
8日間+3250キロの長丁場
30周年記念大会の幕が開けた
早朝6時。まだ寝静まっていたホテル中央のロータリーに、突如2輪の排気音が響き渡る。やはりレシプロエンジンはいい。長丁場に立ち向かうライダー達の意図と決意を、その鼓動から感じることができる。
1台、また1台とアジアパタヤホテルを後にする選手達。最初のロードセクションは116km。タイム計測が行われるスペシャルステージ(SS)までの一般公道だが、2時間半のターゲットタイムが与えられ、交通法規を守りながら時間内に到着することが求められる。
競技1日目(LEG1)のSSは全行程で199.13km。かなり長めの設定だ。ただし、中盤に設けられた「PC(パッセージコントロール)ストップ」で一旦タイム計測が中断され、すぐ側のサービスエリアでメカニックによるサービスが受けられる。
その後再び「PCスタート」でタイム計測が再開され、SSゴールまでの時間が正確に計測される。このSSタイムが毎日積算され、8日間のSS走行に要した積算タイムで優勝が争われる。なお、SS走行にも「MAXタイム」が設けられており、これをオーバーするとペナルティタイムが加算される仕組みだ。
また、ホテルからSS、SSから次のホテルを結ぶロードセクション(RS)は定められた時間内に走ることが求められ、それに違反してもやはりペナルティがタイムが加算される。したがってSSタイムがいかに速くてもRSで1度でもトラブルに見舞われると総合優勝は難しい。SSはもちろんRSも含め、最終日のゴールまでトラブルなく走ることが上位入賞の大前提。プライベーター達が「完走」を第1の目標に置くのもそのためだ。
この日のSSは山や急な丘はなく、全行程が比較的平坦な道だ。ゴムの木のプランテーションの農道などが多い。だが路面は凄まじく悪かった。そこかしこに穴があり、それも左右輪が同時通過せねばならないような厳しい状況が多数。ジムニーのホイールベースより大きな穴もあったとの話で、特にサスペンション改造が少なめなプライベーターのチームが苦労していた。
また、その穴に水が溜まり、泥がたまり、穴そのものがわかり辛かった上、スリッパリーな泥と路面の凹凸によってマシンが左右に振られ、真っ直ぐ走るのも難しいほど。もちろんタイムはできるだけ縮めたいがスピードを上げるとサスペンションに無理がかかり、ドライバー達は心理的にもストレスが溜まっていく。
さらに、両脇のブッシュに大きな岩や切り株が隠れていることも多く、しびれを切らしたチームがここを高速で通過することで大きなトラブルに見舞われる、というアクシデントが多発した。
四輪では前後輪同時にバーストした者、フロントサスを破損させてタイヤがあらぬ方向を向いたまま走り続ける者、上下逆さまになる者、止まりきれず衝突する者、池に落ちる者など、ラリーは序盤戦から大荒れの様相となった。
実際、出走44台中、故障やアクシデント、スタックによるMAXタイムオーバー、RSのターゲットタイムオーバー等で10時間以上のペナルティを受けたマシンは13台。実に3割のマシンが大きく戦線を離脱していった。
そんな中、13番手スタートながら3時間16分39秒のベストタイムを叩き出したのは ♯113 TOYOTA GAZOO RACING THAILAND の Natthaphon Angritthanon(タイ)/ Thanyaphat Meenil(タイ)組のトヨタ ハイラックスだ。
ナタポン選手は2013年大会からコロナ前の2019年まで、実に7年連続優勝という前人未到の偉業を成し遂げたレジェンドだ。コロナ後は2024年からAXCRに復帰、今年はマシンも戦闘力の高いものに強化していたが、やはり、ここ1番の強さを発揮してきた。
ナタポン選手は優勝スタイルはとてもシンプルだ。初日にトップに躍り出て最終日までその座を守り切るというものだが、走りが安定しているため、誰も彼を抜くことができず、2位以下とのタイム差はむしろ開いていく一方になりやすい。
今年は、4年目の王座奪還をかけてチーム三菱ラリーアートがトライトンをかなりのレベルにまで仕上げてきているので、2位につけた ♯112 MITSUBISHI RALLIART の Chayapon Yotha(タイ)/ Peerapong Sombutwong(タイ)組との戦いも見物だ。
なお、この日の四輪には大会スポンサーのPROPAKから1位〜5位の選手にアワードが用意されていた。19時からオープンしたディナー会場で宴たけなわになった頃、SS上位の選手がひとりずつ壇上に呼ばれ、アジアンラリー親善協会の石田憲治会長から賞金のアワードを受け取り、嬉しそうに記念写真に収まっていた。
プライベーターを含む、詳しいレースレポートはまた後日。
まずは、山岳地帯で繰り広げられるLEG2の戦いを見守りたい!
(文/河村 大、写真/高橋 学)
Moto
順位争いは、まだまだこれからのタイヘンな1日目
迎えた初日、朝のスコールも無く好天に恵まれ(日本に比べれば)湿度も低く、気温も(日本に比べれば)それほど高くもない東南アジアの夏。絶好のラリー日和に恵まれたところで、40台にもおよぶバイクがタイを舞台に繰り広げられるラリーがスタートした。
これほどまでに(日本に比べれば)清々しい朝を迎えることが出来るとは、参加者にとってなんともありがたいことだろう。
だが……前日に配布されたロードブック(バイクの場合は冊子ではなく巻物のコマ図)のボリュームに、前日深夜におよぶまで早くも苦戦を強いられることになった。
Auto(4輪)と違ってMoto(2輪)の場合、自分でマップを読み解きながら運転しなければならないため(クルマの場合はコドラという助手席の人間がマップを読みながら進むべき方向をドライバーに指示する)、ハンドル付近に「ロードブックホルダー(日本ではマップホルダーという呼び名が一般的)」を別途装備し、電動で巻物を送りながら距離を測りつつ進むべき方向を自分で判断し、自分でマシンを操作しなければならない。
コマ図の解読は例年同様困難極まりない内容だが、今年の「巻物」はさらに一味違っていた。とにかく太い……直径10cmを超えるほどの紙の「恵方巻」状態だったのだ。
果たしてこの顎が外れそうなくらいボリューム満点のマップをどう処理すべきか……それが、前日深夜まで参加者を悩ませていた問題だった。
というのも、マップホルダーに巻けることが出来る紙のボリュームは限られ、それはメーカーによっても異なり、競技者は各々これがベストだろうと思うマップホルダーを準備している。
その全てを凌駕する、規格外のマップのボリュームに、どのマップホルダーも全てを飲み込んで正しく作動させることは出来ない、という状況に一同愕然……。
前日の公式ブリーフィーングで大会主催者(日本人)はこう言った……「Motoクラス、どうする? コレ?(苦笑)」と……。
ここでクレームを言うバイク乗りは1人もいない。「おやおや、どうしたものか……」と、走り出す前に目の前に立ち塞がる障害に対して如何に対処すべきかを脳内でグルグルと演算する。
結果として「太巻き」問題はそれほど大したことではなかったようで、もちろん、2分割、3分割、4分割によってどこでマップを巻き替えるかの手間はあるが、それなりにこなした模様。
ちなみに、LEG.1のマップは一部LEG.5と共有するため、使い終わったら破棄、というバイクならではの手法は使えないため、そこだけは強く「巻き終わったマップを捨てるな」と、オーガナイザーから念押しをされていた。
さておき、レースリザルトに関して興味のある方は日々チェックしていただきたい。スプリントとは異なり、休息日を含む全8日間に及ぶ日程の本ラリーレイドにおいて、こまごまとしたペナルティ(加算)による順位の変動は、始まったばかりの段階では如何とも言い難いところ。
強いて注目選手を挙げるのであれば、日本人ではアジアンラリーの古参、ベテランラリーストである池町選手や、前年優勝者の松本選手、そしてアジアンラリーには9年ぶりの参戦となる、モンゴルや日本の競技ラリーで(言い過ぎかもしれないが)絶対王者とも言われる泉本選手のウェルカムバックだろう。
そしてそんな彼らの前に立ちはだかる真の実力ラリースト、それは母国タイ王国出身のジャクリット選手、およびスマティ選手だろう。
ちなみに、両者はいずれも日本人選手との交友関係が深く、ときには命にかかわるほどの出来事を通じて国境を越えて深い信頼関係を構築している。それもまたライリーレイドという競技の魅力のひとつと言える、他では得難いコミュニケーションと言えるのではないだろうか。
その一方で、忘れてはならないのが日本から初参戦となる若きチャレンジャーの面々。こちらに関しては日を追うごとにそのポテンシャルを発揮できるのかできないのか、見守りながらその実情をお伝えしたいところで、現状では「無事に頑張っている」以外にお伝え出来ることも無く、気が付けば周囲の「優しいおじさんたち」が彼らをサポートしている姿がときに微笑ましく、これもまた「助け合い」の精神が宿るバイクのラリーなのではないか、とつくづく思わされるところでもある。
30周年記念を迎えたアジアンラリーは1日目を終えたばかり。とくにMotoクラスに関しては、この先も目が離せない展開が待っていることだろう。
(写真・文/田中善介)