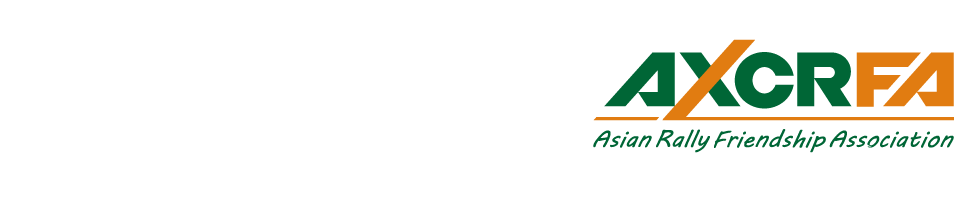LEG3
8月11日(月)カオヤイ
身も心も競技に慣れ始める中盤戦
それを活かすも殺すもチーム次第
サービスクルーの朝は早い。ホテルからマシンを定刻にスタートさせるために夜が開ける前から準備をしなければならないからだ。朝からエンジンがかからない、なんてことは許されない。
3日目の朝ともなると彼らの目は腫れぼったくなってくる。夜を徹した作業でろくにベッドに入ることもできないからだ。でも眼光だけは鋭く、グループワークも手慣れてくる。体もタイの気候と水に順応し、疲れているのに体がよく動く。
この時期、ドライバーやコ・ドライバーもAXCRに順応し始めるが、サービスクルーの体にも同じ事が起きる。この「慣れ」をチームが前に進むベクトルに変えて行けるか否か。はたまたケアレスミスを誘う気の緩みを生み出す負のベクトルに変えてしまうのか…。そのハンドリングが、チームを預かるリーダー達の腕の見せ所でもある。
序盤の深手から這い上がり、団結して強くなるチームもあれば、トラブルフリーの手応えに慢心し、順位への偏心や作業、待遇への不満が一人歩きしてしまうチームもある。
見えないところでチームが生き物のように強くなったり、脆く崩れやすくなったり。まるで人生のような筋書きのないドラマを楽しめるのがクロスカントリーラリーの面白さでもある。そして、それが一番起こりやすいのがAXCRの中盤戦なのだ。このラリーに必要なのはマシンの性能だけではない。深く試されるのは人間力。AIでは決して真似することのできない人間ドラマが今日も続いて行く。
さて、想像以上の厳しさとなった大波乱の序盤を越え、迎えた3日目のルートはSSが195.75km、RSが164kmという設定。SSは長いが移動距離がやや短めだ。スタートは標高600メートルの丘陵の上。序盤はやや下り方向の走りでエンジンへのストレスは少なめだが、昨日のSS同様、岩や溝の多い山岳地帯での戦いとなり、大きな岩や段差を越えながら、いかに走りやすいラインを見つけ、マシンを壊さず、安定して速く走れるかが勝負となる。
後半はタイヤが半分以上隠れるようなサンド地形も出現し、排気量が小さく、大型車の作った轍と合わせて走れないジムニー勢はかなり苦戦していた模様だ。そして昨日に続き今日も午後に襲ってきたのが「スコール」だ。突然、大粒の雨で視界が遮られ、雷が鳴り響き、それまでカチンカチンに乾いていた路面が極悪マッドへと一気に変わって行く。
ここ数年、AXCRは雨に恵まれず、乾燥したダート路を高速で争うスピードバトルへと変化しかけていたが、今年は主催者の狙い通り。自然のダイナミズムをも味方に付けた「極悪」コースのAXCRが復活している。
いすゞ・トヨタ・三菱の三つ巴の戦いにも注目!
そんな中、一番時計で飛び込んで来たのは ♯101 TOYOTA GAZOO RACING THAILAND の Mana PORNSIRICHERD(タイ)/ Kittisak KLINCHAN(タイ)組の トヨタ ハイラックスだ。序盤戦、やや控えめに見えた昨年の覇者が、3日目にしてその本領を発揮。2位を4分以上突き放す渾身の走りで、ライバルを圧倒してみせた。ハイラックスは「そのままでもラリーに出られる」と言われるほど頑強なフレームを持つクルマだが、地形の激しいこのSSでもスピードをある程度落とさずとも走れる強さと安心感をドライバーに与えてくれていたに違いない。
ただし、昨日まで総合トップに居たチームメイト ♯113 の Natthaphon Angritthanon(タイ)/ Thanyaphat Meenil(タイ)組は序盤にサスペンショントラブル、後半にもアクシデントを起こし、トップから1時間以上遅いタイムで優勝戦線から大きく外れてしまっている。
続く2番手は♯102 ISUZU SUPHAN YOKOHAMA LIQUI MOLY RACING TEAM の Suwat LIMJIRAPINYA(タイ)/ Prakob CHAOTHALE(タイ)組の いすゞ D-MAXだ。
いすゞの SUPHAN 勢といえば、一昨年までは「一発の速さはあるものの、後半までマシンが持たない」のが常だったが、昨年からは耐久力も身につけ、前後半を通してトップ争いに絡む常連チームに成長している。今年も初日からの順位は3位、5位、2位。安定した速さで総合でも2位につけ、セミワークスチームながら、ワークスのトヨタ、三菱を脅かす存在となっている。
そして2位から僅か6秒差の3番手に付けたのは ♯112 MITSUBISHI RALLIART の Chayapon Yotha(タイ)/ Peerapong Sombutwong(タイ)組の三菱トライトン。これにより、3日目にして念願の総合トップの地位を手に入れた。昨年、終盤まで総合トップを快走ながら、エンジントラブルにより涙を飲んだチャヤポン選手だが、今大会もクルマを壊さず、ステディでスムーズかつ速い走りは健在。総合でも2位に11分以上の差をつけ、一躍優勝候補の最前線に躍り出た。
増岡 浩 総監督はラリー前、「我々のエンジンは2.4リッター。トヨタの2.8リッターに対して負っているビハインドを、昨年はエンジンチューンでカバーする作戦だったが、それが裏目に出てしまった。今年は速さに加え、耐久性重視でセットアップしてきたので、手応えは十分。あとは選手達の活躍に期待したい」と語っていたが、果たしてこのままゴールまで快走してくれるのか、このあたりも注目して行きたいポイントだ。
なお、トライトンを操る選手達が今大会で使っている駆動モードは「H4」というフルタイム4WDモード。このモードでは前40、後50の不等トルク配分が行われ、四駆でありながらFRのような素直なハンドリングが楽しめる。それだけではない。各輪のブレーキ制御を応用したアクティブ ヨー コントロールにより、コーナー出口に向け、ノーズがグイグイ入っていく性能をも併せ持っている。これら市販車に与えられた最新のテクノロジーが、トライトンを "希代のハンドリング ピックアップ" に仕立てあげているわけだが、これが実際、クロスカントリーラリーの世界でどう活きてくるのか? 次世代のピックアップ市場の覇権を掛けた、トヨタVS三菱、そしていすゞの三つ巴の戦いにも大いに注目して行って欲しい。
この日は、四輪のトップタイム5台にヨコハマゴムのアワードが与えられていた。ディナー席の壇上に真っ先に呼ばれたのは♯101 TOYOTA GAZOO RACING THAILAND の Mana 選手。そして二番手が♯102 ISUZU SUPHAN YOKOHAMA LIQUI MOLY RACING TEAM の Suwat 選手、三番手が♯112 MITSUBISHI RALLIART の Chayapon Yotha 選手である。それぞれが、トヨタ、いすゞ、三菱を代表する存在だ。総合でもトップ3となる3名の主役の登場に、会場からも大きな拍手が湧き起こっていた。
(文/河村 大、写真/高橋 学)
Moto
早くも実力者たちが上位へ浮上。ラリー成分を存分に吸収し始める3日目
スタートとゴールが同じポイント(滞在ホテル)となるループ設定の競技3日目。Leg.3の総走行距離は360.50kmと比較的コンパクトで、最初に出走するライダー(全競技者の中で1番目)の出発時刻も07:00と期間中では遅め。SSまでのターゲットタイムは1.5時間(SSスタート地点までの距離66.94km)でSSのスタートは08:35という設定だった。
この日は前日までの比較的平坦な土地を巡るコースとは異なり、標高差を楽しめるアップダウンの山岳路が含まれる。未舗装路は概ね締まった赤土や白砂の砂利ダートで、昨晩から今朝にかけてのほどよい雷雨の影響は大きな水たまりや泥濘を作ることもなく、また激しく砂埃が舞うことがないベストコンディション。そして山岳部ではカチコチの岩盤が剥き出しで砕けた岩が転がるガレ場がこの日の「鬼門」となっている。
ガレ場と言っても、日本の林道のように握りこぶし大の石がゴロゴロ置かれているわけではなく、砕けた岩盤の尖った石のほとんどが地面に固定されて動かないため、登りでも下りでも足元をすくわれずにタイヤはしっかりとグリップしてくれる。
厄介なのは濡れている場合で、地上に顔を出した岩盤は水に濡れると驚くほどよく滑る。登りは登れず、下りはただ重力に身を任せて落下するように進むだけ。ブレーキ操作を誤ると一瞬で転倒する……が、幸いそんな状況でもなく、深い轍や尖った石に注意を払ってラインを見極め、じんわりと駆け抜けるのが得策と言える。
しかし常に上位に名を連ねる実力ライダーは違うようで、この日、母国タイ王国出身のアジアンラリー絶対王者であるジャクリット選手(#46/KTM 500EXC-F)は、土地に慣れているという理由だけでは語れない異様な速さでSSを駆け抜け、前日までの5位以下から一気にトップへ躍り出し、初日から2日間1位に座していた池町選手(#16/HUSQVARNA FE350)は2位、次いで同じくタイ王国出身のスマティ選手(#17/KTM 250XCW)が3位、そして4位変わらずの泉本選手(#22/HUSQVARNA FE450)と続いている。
もちろん、速さだけでは上位に留まれないのがラリーなわけで、まずルートミスが少ないこと、ペナルティが無いこと、マシンや自身にトラブルが起こらないことが大前提の勝負であり、そしてそれはほんの一瞬のミスで大きく結果に影響する。
Leg.3でもやはりまた迷走者が続出し、上位以下は自ずからトップとのタイム差を大きく広げた結果となっている。マシントラブルなど早々に戦線離脱する者や、「乗れている」自分に調子を良くして前転してしまった者もいる。
色々な意味を含んだ「速さ」を身に着けた者は淡々とペースを維持するのみで、下位との差はどんどん広がっていくという循環なのだろう。上位へ浮上するのは、なかなかムズカシイものだ。
ちなみに、上位10名のうち半数が日本人選手を占めており、たまたま10位以下だったという実力派日本人ライダーも参戦している。参加者の1人は、常に競い合えるライバルがいることに「なんか楽しいよなぁ、嬉しいわ」と語る。その言葉は印象的だった。
競技の特殊性から、そういった経験者・実力者が古参揃いになってしまうのは仕方のないことだが、一方で無謀とも言える挑戦に来た若手もいるから面白い。数こそ少ないが他の海外ラリーに比べて圧倒的な敷居の低さがアジアンラリー最大の特徴と言えるかもしれない(特に費用面で)。続かなければ、少しでも多くの人の記憶に残ることもないだろう。
おそらく日々のレポートで必ず触れるであろう「コマ図の解読が困難」問題について。ベテラン勢へ率直に「なんで迷わず進めるの?」と聞けば、まず「いや、迷ってるよ。すぐにリカバリーしてるけど」と、続いて「経験してるから」、「野生の勘でしょう」、「慣れてるから」という回答がほとんどだった。今すぐ参考に出来ることでは全くないが、それ以上に言いようがないのだろう。積み重ねてきた経験とノウハウ、蓄積がモノを言うということだ。
多くの日本人ライダーが参戦するアジアンラリーの公式サイトでは、エントリーリストも公開されている(もちろん4輪やサイドカー、海外勢も)。どんなバイクで走っているのかも確認出来るし、レースリザルトと照らし合わせて顔も見える。これからも異国の地を走るライダーたちの姿をたくさん撮影して本サイトで紹介していくので、競技が終了する最後まで、是非楽しんでもらいたい。
(写真・文/田中善介)